はじめに
皆さんこんにちは!
この記事では、「CISPR規格とは?」 をテーマに、初心者の方でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。
電磁両立性(EMC)の分野では「規格」という言葉を頻繁に耳にしますが、その中でも特に重要なのが
「CISPR規格」 です。
製品開発や国際市場への展開を考える企業にとっては避けて通れないテーマですね。
- 「CISPRってそもそも何の略?」
- 「どんな規格が含まれているの?」
- 「どんな製品に関係してくるの?」
この記事を読めば、こうした疑問がスッキリ解決できるはずです。
CISPRとは?
CISPRの正式名称
CISPRは、「Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques」 の略称です。
日本語に訳すと「国際無線障害特別委員会」となります。
誰が運営しているのか
CISPRは、IEC(国際電気標準会議) の下部組織の一つです。
IECは電気・電子技術に関する国際標準化を担う機関で、CISPRはその中で特に「無線障害=不要電波」に関する標準化を担当しています。
CISPRの役割
CISPRの主な目的は以下の通りです。
- 製品から出る不要な電磁波(エミッション)を規制する
- 他の機器に影響を与えないよう基準を整備する
- 各国が共通で利用できるEMC試験方法を定める
つまりCISPRは、「世界中で共通に使える電磁波規制のルールブック」 を作っている存在です。
なぜCISPR規格が重要なのか?
製品の市場参入に必須
製品をヨーロッパやアジアなどの海外市場に輸出する場合、CISPR規格に適合しているかどうか が必ずチェックされます。
これに適合していなければ、販売許可が下りないケースもあります。
消費者の安全と快適性を守る
もし規格がなかったら…
- テレビに雑音が入る
- スマートフォンの通信が途切れる
- 医療機器が誤作動する
このようなトラブルが頻発するでしょう。CISPR規格は、社会全体の安心・安全を守るための基準でもあるのです。
国際的な整合性
各国ごとに独自の規制を作ると、企業は市場ごとに試験・設計をやり直さなければなりません。
CISPR規格があることで、国際的に統一されたルールで製品を設計・試験できるメリットがあります。
CISPR規格の分類
CISPRには、対象となる製品や試験方法ごとに細かい規格が存在します。代表的なものを紹介します。
CISPR 11
- 対象:産業用・科学用・医療用機器(ISM機器)
- 例:MRI装置、溶接機など
CISPR 22 / CISPR 32
- 対象:情報処理機器(IT機器)、マルチメディア機器
- 例:パソコン、プリンタ、テレビ、AV機器
- CISPR 22(旧規格)からCISPR 32へ統合
CISPR 14
- 対象:家電製品、小型機器
- 例:冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電動工具
CISPR 15
- 対象:照明器具やLED照明
- 例:蛍光灯、LEDランプ
CISPR 25
- 対象:車載電子機器
- 例:カーナビ、車載充電器、ECU
📌 まとめ表
| 規格番号 | 対象機器 | 代表例 |
|---|---|---|
| CISPR 11 | 産業・医療機器 | MRI、溶接機 |
| CISPR 32 | マルチメディア機器 | PC、テレビ |
| CISPR 14 | 家電製品 | 掃除機、洗濯機 |
| CISPR 15 | 照明機器 | LED、蛍光灯 |
| CISPR 25 | 車載機器 | ECU、充電器 |
CISPR規格で定められている内容
CISPR規格では大きく分けて2つの内容が定められています。
エミッション(放射するノイズ)
- 機器が外部に出してしまう電磁波
- 伝導エミッション(ケーブルから伝わるノイズ)
- 放射エミッション(空中に放射されるノイズ)
測定方法
- 試験に使う測定器(EMIレシーバー、LISNなど)
- 測定環境(電波暗室、オープンサイト)
- 測定距離、周波数範囲、アンテナの種類
つまりCISPRは「ノイズの許容値」と「測定のルール」の両方を規定しているのです。
CISPR規格と他の規格の関係
IECとの関係
CISPRはIEC(国際電気標準会議)の特別委員会であり、発行されるCISPR規格はすべてIECの公式規格として管理・出版されています。
ただし名称は「CISPR xx」として残るのが一般的で、「IEC ○○」という番号に置き換わるわけではありません。
補足コラム:CISPRとIECの関係
💡 ここで整理しておきましょう!
- CISPRはIECの傘下組織
→ 不要電磁波やEMCの国際規格を専門に扱います。 - CISPR規格はIECの公式規格として発行される
→ 出版や販売はIECが行い、IECのカタログに掲載。 - 規格番号は「CISPR xx」のまま残る
→ 例:CISPR 11、CISPR 32。
→ 「IEC 12345」と別番号になるわけではありません。 - 他のIEC規格から参照されることも多い
→ 製品規格やgeneric EMC規格の中でCISPRを引用。
✅ まとめると
CISPR規格はIECの国際規格体系の中で利用されており、
「IECが出版するCISPR規格」 と理解するのが最も正確です。
EN規格(ヨーロッパ)
ヨーロッパでは、CISPR規格をベースにしたEN規格が使われます。
CEマーキングを取得するためにはEN規格への適合が必須です。
FCC規格(アメリカ)
アメリカではFCC Part 15などが主流ですが、試験方法はCISPRと類似しており、互換性があります。
CISPR規格の試験の流れ
- 対象規格を特定する
(例:家電ならCISPR 14、情報機器ならCISPR 32) - 試験環境を準備する
(電波暗室、LISN、アンテナなど) - 伝導エミッション試験
ACラインやDCラインのノイズを測定 - 放射エミッション試験
アンテナを用いて空中のノイズを測定 - 規格値との比較
測定結果が規格値以下なら「合格」
初心者が知っておくべきポイント
- 規格は更新される → 古い規格では認証が取れない場合がある
- 国ごとに適用が異なる → EU、北米、アジアで微妙に要件が違う
- 設計段階で考慮することが重要 → 試験直前に慌てるのはNG
まとめ
- CISPR規格とは、国際的に統一されたEMC基準のこと
- 不要電磁波(エミッション)の規制と試験方法を定めている
- 対象ごとに複数の規格があり、製品開発に必須
- 国際市場参入や製品の信頼性確保に欠かせない
初心者の方でも、CISPR規格の全体像を理解することで、製品開発の流れや国際ルールの背景がつかみやすくなるはずです。
これからEMC分野を学ぶ方は、まず「自分の製品に関係するCISPRはどれか?」を調べるところから始めるとよいでしょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました!!




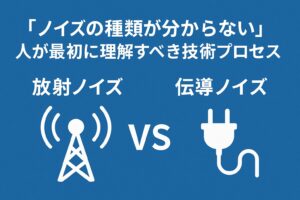
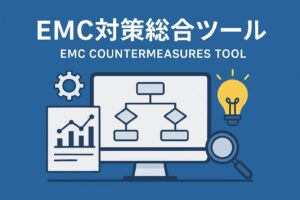



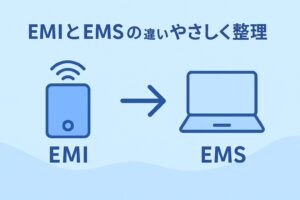

コメント