はじめに
皆さんこんにちは。
今日は「新人エンジニアが最初に覚えるべきEMC測定器ベスト5」というテーマでお話しします。
(あくまで私の独断と偏見ですが(笑))
私は試験所で働きながら日々EMC試験に関わっていますが、新人の頃は 「測定器の名前すら分からない」
「操作方法が複雑で怖い」 という状態からスタートしました。
EMCの世界では、普段の電気電子分野ではあまり触れない専用測定器が多く登場します。そのため、最初は誰でも戸惑うものです。
しかし、基本的な役割と使い方を理解すれば、実務で大きな自信につながります。今回は、新人エンジニアがまず覚えるべき、現場で必須となる5つの測定器を厳選しました。
ラインナップはこちらです。
- スペクトラムアナライザ
- EMIレシーバー
- LISN(疑似電源回路網)
- アンテナ
- 信号発生器
それでは、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
1. スペクトラムアナライザ
基本的な役割
スペクトラムアナライザ(通称スペアナ)は、周波数ごとに信号の強さを測定する装置です。
オシロスコープが「時間軸」で波形を観測するのに対し、スペアナは「周波数軸」で信号を分析します。
「どの周波数に、どれだけの成分が含まれているか」を可視化できるため、EMCの最初の入口として欠かせません。
仕組みのイメージ
スペアナは内部で信号を周波数ごとに分離し、パワーを測定しています。
ラジオのチューナーを高速で動かして「全周波数を一気にスキャンしている」とイメージするとわかりやすいです。
EMCでの利用シーン
- 製品から発生するノイズの周波数成分を確認
- アンテナで受信した電磁波のレベルを測定
- 簡易的な事前試験で規格値との差を把握
新人がつまずきやすいポイント
- RBW(分解能帯域幅)の設定で結果が大きく変わる
- dBm・dBμVなど単位の違いに混乱する
- ノイズフロアを信号と誤認しやすい
- 入力信号が強すぎてオーバーロードする
体験談
私も最初は「画面にノイズがいっぱい出てる!」と焦っていましたが、実際は測定条件が悪かっただけ…。
先輩に「まずはRBWとATTを確認しろ」と言われ、基礎の大切さを痛感しました。
さらに一度はオーバーロード状態で測定してしまい、怒られたのもいい経験です(笑)
2. EMIレシーバー
基本的な役割
EMIレシーバーは、EMC規格(CISPRなど)に準拠した方法でノイズを測定する専用装置です。
外見はスペアナに似ていますが、内部に規格準拠の帯域幅や検波方式が組み込まれています。
「スペアナは万能だが規格試験には不十分、EMIレシーバーは規格適合専用」というイメージが正しいです。
EMCでの利用シーン
- 電子機器の正式試験
- CISPR規格に基づく伝導エミッション測定
- 放射エミッション測定での規格適合チェック
新人がつまずきやすいポイント
- スペアナとの違いが分かりにくい
- 測定スピードが遅く「壊れてる?」と勘違いする
- 検波モード(Peak, Quasi-Peak, Average)の意味が分からない
体験談
私も新人の頃、「スペアナで測れるならレシーバーはいらないのでは?」と思っていました。
しかし、規格適合試験には必須。特にQP(Quasi-Peak)検波が「人間の聴感特性を模したもの」と知ったときは、測定の奥深さに驚きました。
単一周波数でチューニングしているうちに、気づけば狙った周波数からズレていたこともあり、基本操作の大切さを学びました。
3. LISN(疑似電源回路網)
基本的な役割
LISN(Line Impedance Stabilization Network)は、電源ラインから伝わるノイズを正確に測定するための装置です。
電源とEUTの間に挟み、一定のインピーダンスを提供しながら、ノイズを測定器に分岐させます。
「電源の条件を一定化して、公平な測定をするための道具」と考えると理解しやすいです。
LISNとは何か気になる方はこちら!!
EMCでの利用シーン
- 伝導エミッション試験に必須
- AC100VやDC電源ラインのノイズ測定
- 再現性ある測定環境の確保
新人がつまずきやすいポイント
- 接続を間違える(L/Nの取り違えなど)
- 接地を忘れる
- LISNの種類(単相・三相、DC用など)を混同
- 内蔵フィルタやATTを正しく設定できない
体験談
新人の頃、LISNの設定を誤り、前回と全く異なる結果が出てしまったことがあります。
先輩から指摘されて気づいたときは本当に冷や汗…。
「LISNは単なる箱ではなく、測定の前提条件を作る大切な装置」だと理解するきっかけになりました。
4. アンテナ
基本的な役割
アンテナは、EUTから放射される電磁波を受信する装置です。
周波数に応じて異なる種類を使い分けます。
主な種類
- バイコニカルアンテナ(低周波数帯向け)
- ログペリオディックアンテナ(中高周波帯向け)
- ホーンアンテナ(GHz帯で高感度)
EMCでの利用シーン
- 放射エミッション試験(3m法・10m法)
- 放射イミュニティ試験での送信側
- アンテナファクタを使った電界強度換算
新人がつまずきやすいポイント
- 種類ごとの周波数範囲を覚えられない
- アンテナファクタを使った計算が難しい
- 向きや高さで結果が激変するのに驚く
- 水平/垂直偏波の切り替えを忘れる
体験談
私は新人時代、アンテナの向きを90度間違えて設置し、結果が大きくズレてしまいました。
上司から「新人あるあるだな」と笑われましたが、現場では笑い事では済まないことも…。
5. 信号発生器(Signal Generator)
基本的な役割
信号発生器は、任意の周波数や波形を生成する装置です。
EMCではイミュニティ試験に用いられ、外部からノイズや電磁波を与えて機器の耐性を確認します。
EMCでの利用シーン
- 放射イミュニティ試験の基準信号源
- 伝導イミュニティ試験でのノイズ注入
- 開発段階での特定周波数ノイズ再現
新人がつまずきやすいポイント
- 出力レベル(dBmとdBμV)の換算ミス
- 単体出力が弱く、アンプとの組み合わせが必要
- 周波数スイープ設定を誤り、規格外の試験をしてしまう
体験談
私が新人のとき、出力単位を勘違いし、大きな信号を出してしまったことがあります。
先輩に止められ、「信号発生器は“攻める側”の装置だから、慎重さが必要」と強く実感しました。
まとめ:5つの測定器を押さえればEMCの基礎が見える
今回紹介した測定器は以下のとおりです。
- スペクトラムアナライザ → ノイズの可視化
- EMIレシーバー → 規格準拠の正式試験
- LISN → 電源ラインのノイズ測定
- アンテナ → 放射ノイズの測定
- 信号発生器 → イミュニティ試験でのノイズ注入
EMCは、「出るノイズを測る(エミッション)」と「ノイズを与えて確認する(イミュニティ)」 の両輪で成り立っています。
今回の5つを理解すれば、その基本が一気に見えてきます。
最初は複雑に見えても、少しずつ慣れていけば「測定器が何をしているのか」が理解でき、試験の意義も分かってきます。
この記事が、これからEMCに挑戦する新人エンジニアの助けになれば嬉しいです。
ここまで読んで頂きありがとうございました!!
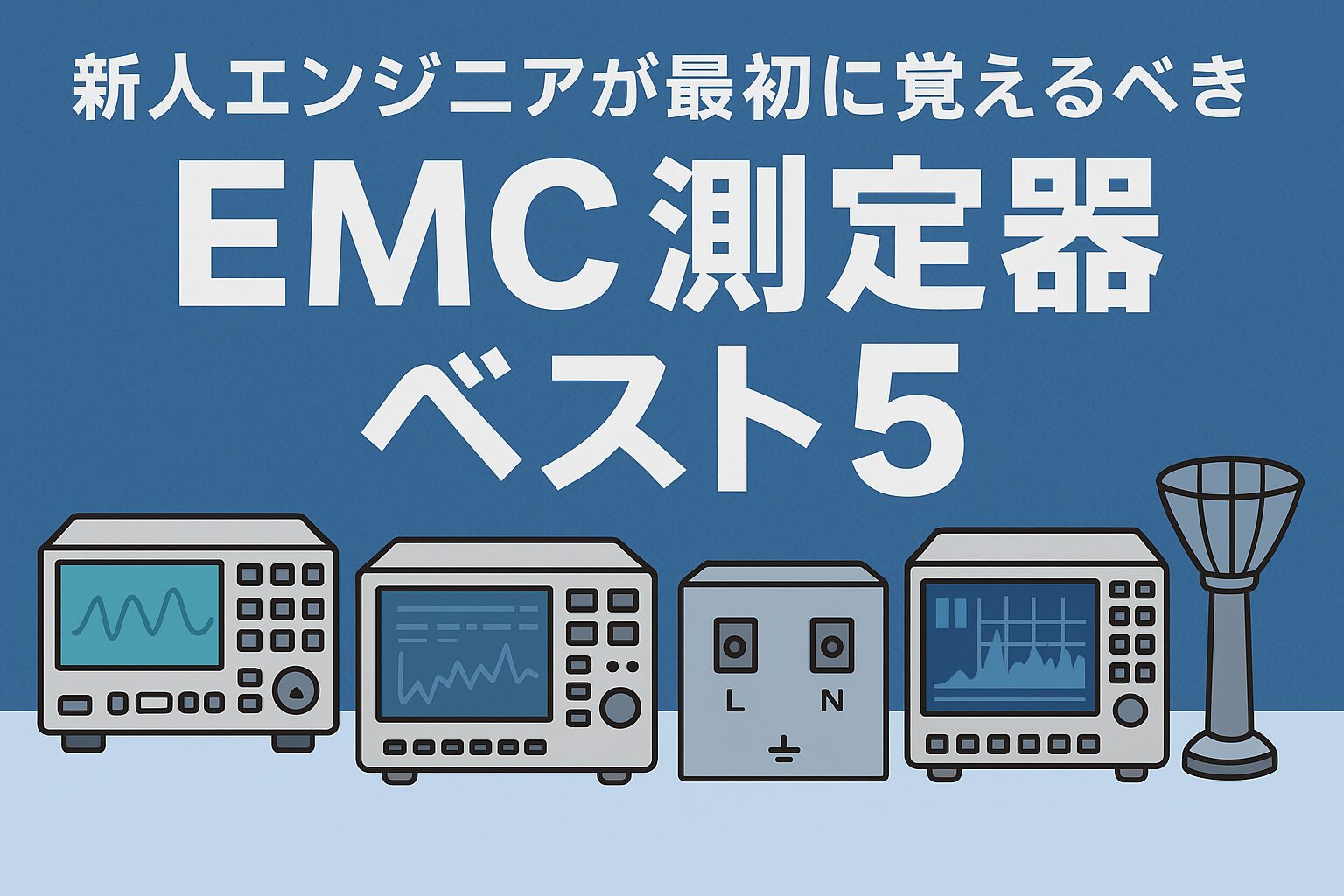
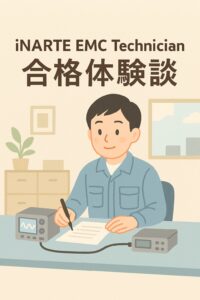


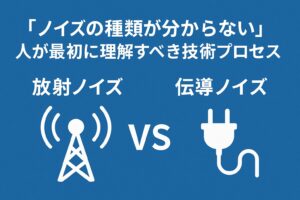
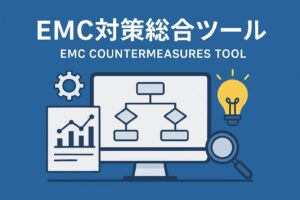



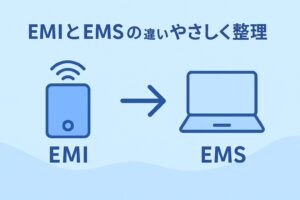

コメント