皆さんこんにちは(^_^)ノ
今日は、EMC(ElectroMagnetic Compatibility/電磁両立性)に関わる仕事を始めたばかりの
新人さん向けに、「最初につまずきやすい用語」をまとめてみました。
私自身も新人の頃は、先輩が使う専門用語がまるで暗号のように聞こえ、頭の中が「???」で
いっぱいだったことをよく覚えています。そこで今回は、特に登場頻度が高く、かつ混乱しやすい用語を厳選して解説します。これを読めば、明日からの会話や資料理解が少し楽になるはずです。
EMC(電磁両立性)
まず大前提の「EMC」という言葉。
これは 「機器が周囲に不要な電磁的な妨害を与えず、かつ他からの妨害を受けても正常に動作する能力」 を指します。
- EMI(ElectroMagnetic Interference) … 他の機器へ与える妨害
(=出してはいけないノイズ) - EMS(ElectroMagnetic Susceptibility) … 他からの妨害に対する耐性
(=どれくらい誤作動せずに耐えられるか)
つまり EMC とは「出すな、負けるな」の2つの視点を合わせた総合的な考え方です。
こちらで解説しているのでどうぞ!!
ノイズ(Noise)
新人が最初に混乱するのが「ノイズ」の種類。
- 伝導ノイズ(Conducted Noise)
電源ケーブルや信号線を通って流れるノイズ。測定では LISN を使って確認する。 - 放射ノイズ(Radiated Noise)
機器そのものがアンテナのようになり、空間に放射されるノイズ。電波暗室でアンテナを
使って測定する。 - 差動モードノイズ(Differential Mode)
2本の線間で流れるノイズ。主に信号由来。ノーマルモードとも言います。 - コモンモードノイズ(Common Mode)
線と大地(GND)に対して同方向に流れるノイズ。EMIで問題になることが多い。
現場では「コモンが強いね」「これは伝導じゃなくて放射っぽい」など、略語的に会話されるので最初は置いてけぼりになりがちです。
LISN(ラインインピーダンス安定化回路)
「リッスン」と呼ばれる測定器具。
電源ラインに流れ込むノイズを規格化された条件で測るための装置です。
LISN の役割は大きく2つ:
- 電源を安定化したインピーダンスに整える
- 機器から出るノイズを取り出して測定器へ送る
新人は「LISNは電源フィルタの仲間?」と誤解しがちですが、あくまで測定のための装置です。
また、規格によって名称が異なっており、CISPR規格ではAMN、FCC規格ではLISN、車載系のCISPR25とかだとANと呼びます。色々あってややこしいですが、LISNと言っておけば間違い無いです。
スペアナ(スペクトラムアナライザ)
ノイズ測定の必需品。
周波数ごとの信号レベルをグラフ化して表示します。
ポイントは 「縦軸=レベル(dBμV)、横軸=周波数(Hz)」。
最初は単位がややこしく感じますが、慣れるとノイズ源の特定に欠かせないツールになります。
EMIレシーバー
スペアナと似ていますが、EMC規格に準拠した測定ができる装置。
違いは「検波方式」や「帯域幅」が規格に合っているかどうか。
例えば CISPR では ピーク(PK)、準尖頭値(QP)、平均値(AV) の3種類の検波が必要になります。
「スペアナで見えたけど、規格測定だとアウト」というケースもあるので要注意です。
こちらで解説を紹介しているのでどうぞ!!
アッテネータ(Attenuator)
信号を減衰させる装置。
測定では、強すぎる信号を弱めて機器を保護したり、インピーダンス整合を取ったりするために使います。
例えば「10 dBアッテネータ」を挿入すると、入力された信号は10分の1のレベルに下がります。
新人は「信号をわざわざ弱めるなんて意味あるの?」と疑問に思いがちですが、測定系を壊さないために欠かせないアイテムです。
こちらで解説をしているのでどうぞ!!
シールド(Shielding)
ノイズ対策の定番ワード。
シールドとは「導電性のある素材で覆って電磁波を遮蔽する」ことを指します。
- ケーブルシールド(編組線で覆う)
- ケースシールド(金属筐体や導電塗装)
「シールドすれば全部解決!」と思われがちですが、実際は接地方法や隙間が非常に重要。新人は「シールドの貼り方」でよく失敗します。
フィルタ(Filter)
電源ラインや信号ラインに入れるノイズ対策部品。
代表的なのは LCフィルタ(インダクタ+コンデンサの組み合わせ)。
- コモンモードチョーク … コモンモードノイズを抑える
- コンデンサ … 高周波成分をバイパスして落とす
現場では「とりあえずフィルタ入れてみようか」という場面も多いですが、闇雲に入れると信号まで減衰することがあるので注意です。
アンテナ
放射ノイズの測定に必須。
周波数帯域ごとに使い分けます。
- ロッドアンテナ … 0.15 MHz~30 MHz
- バイコニカルアンテナ … 30 MHz~300 MHz
- ログペリオディックアンテナ … 200 MHz~1 GHz
- ホーンアンテナ … GHz帯
※30MHz~1GHzを一括で測定出来るハイブリッドアンテナ等もあります。
新人が混乱するのは「アンテナゲイン(dBi)」や「校正データ」の扱い。測定値にそのまま足したり引いたりするため、理解していないとレポートで大きな誤差が出ます。
規格(CISPR / IEC / FCC など)
最後に、避けて通れないのが「規格」。
- CISPR … 国際的なEMI規格(民生機器向けが多い)
- IEC … 国際電気標準会議。耐性試験(EMS系)が中心
- FCC Part 15 … アメリカのEMI規格
- VCCI … 日本独自のEMI認証団体
新人の頃は「どの規格を見ればいいの?」と混乱しがち。まずは自分の製品分野(民生・車載・
医療など)で適用される規格を押さえることが大切です。
まとめ
今回は、新人が最初につまずくEMCの用語を紹介しました。
- EMC … 出すな&負けるな
- ノイズ … 伝導/放射、差動/コモン
- LISN … ノイズを測るための基準回路
- スペアナ … ノイズを可視化する測定器
- EMIレシーバー … 規格測定用の測定器
- アッテネータ … 信号を弱める安全装置
- シールド … 遮蔽対策
- フィルタ … ノイズを落とす部品
- アンテナ … 放射測定の必須アイテム
- 規格 … 製品分野ごとのルール
どれも現場では当たり前のように使われますが、最初は意味が分からず混乱すると思います。
ひとつずつ理解していけば確実に力になりますので、焦らず学んでいきましょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました!!

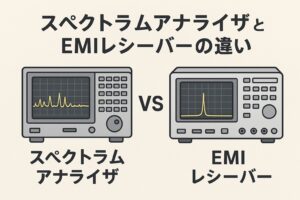


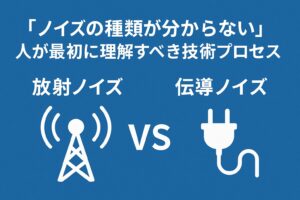
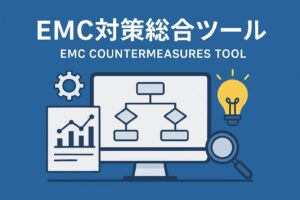



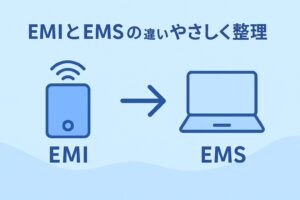

コメント