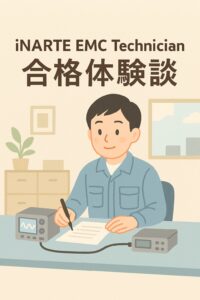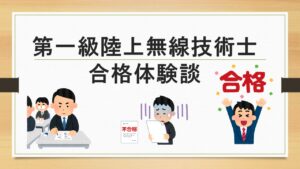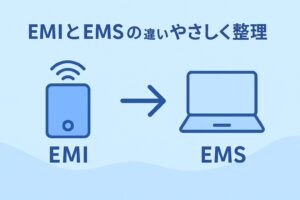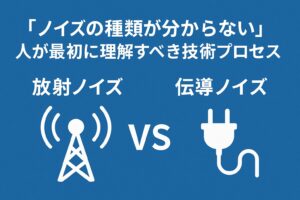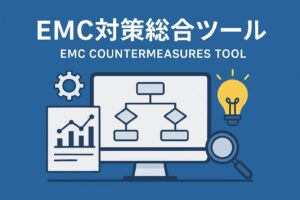はじめに
皆さんこんにちは。
今日は、私が挑戦した 「iNARTE EMC Engineer」 の合格体験談をお話しします。
EMC(Electromagnetic Compatibility:電磁両立性)に携わるエンジニアなら、一度は耳にしたことがある資格ではないでしょうか。
この資格は、国際的に通用するEMCエンジニア資格として知られており、
試験はKEC(一般社団法人KEC関西電子工業振興センター)が日本の試験運営を担当しています。
私自身、最初の受験では不合格という悔しい結果に終わりましたが、翌年の再挑戦で無事に合格を手にすることができました。
この記事では、その過程を包み隠さず、リアルな体験談としてまとめています。
iNARTE EMC Engineerとは?
まず簡単に資格の概要を整理しておきましょう。
iNARTE(International Association for Radio, Telecommunications and Electromagnetics)は、EMCをはじめとした電磁分野の専門資格を認定する国際機関です。
日本では、KECが公式パートナーとして試験運営を行っており、「EMC Technician」、**「EMC Engineer」**の2段階があります。
EMC Engineerは、EMCに関する知識や実務経験を総合的に問う資格で、試験+実務経験+推薦状が合格要件です。
特に実務経験が重要視されるため、試験問題も現場を理解していないと難しいものが多いです。
※実務経験が足りていなくても受験自体は出来ます。推薦状も上司とかに貰えば問題無いです。
試験形式の変化:対面からWeb試験へ
私が受験したのは、ちょうどコロナ禍で対面試験からWeb試験へ移行した時期でした。
以前はKECの試験会場に行って、紙の問題冊子に回答する形式でしたが、私の受験時には完全にオンライン方式へと切り替わっていました。
このWeb方式では、受験前に顔写真付きの身分証明書の提出が必要になります。
さらに、パソコンのカメラとスマホのカメラを同時に使用して監視される仕組みが導入されており、不正行為ができないようになっています。
(スマホは後ろからの映像を送る形で設置します)
つまり、「家で受験できる」とはいっても、実際にはかなり厳重な監視下で行われるオンライン試験です。
出題形式と難易度
試験はすべて 日本語で出題 されます。
問題形式は選択式(4択が中心)で、EMCの基礎理論、測定法、設計、法規、規格など幅広い範囲から出題されます。
特に、「CISPR規格」「ISO 11452」「IEC 61000シリーズ」など、実務で関わる規格内容を理解していないと難しい問題が多い印象です。
1回目の受験:まさかの不合格
正直に言うと、1回目の受験時はあまり勉強していませんでした。
理由は単純で、**「オープンブックだから何とかなるだろう」**と思っていたからです。
iNARTE試験は、参考資料を見ながら解答できる「オープンブック方式」です。
そのため、多くの人が「資料を見ながら答えられるなら簡単じゃない?」と思いがちですが……
実際には、資料を探している時間がもったいないのです。
特に問題文が長く、実務のシナリオ形式になっている場合は、どの規格を参照すべきかを瞬時に判断しなければなりません。
1問ごとに調べていては到底時間が足りず、結果として知識不足+時間切れで不合格となってしまいました。
使用した参考資料:中部エレクトロニクス振興会のiNARTE対策資料
私が試験対策として使ったのは、**中部エレクトロニクス振興会(CECA)**が発行している「iNARTE試験対策資料」でした。
これは、KECの講習会や過去問内容を整理した、非常に実践的な資料です。
内容としては:
- EMC測定の基本
- 規格体系の整理(IEC、CISPR、ISO)
- ノイズ対策部品と回路例
- 測定器の使い方・試験環境
などが網羅されています。
実際、試験問題の多くはこの資料の範囲内でカバーできる印象でした。
1回目の不合格後、この資料を重点的に読み直したのが大きな転機でした。
2回目の受験:同じ問題に救われた
2回目の受験では、正直なところ「前回の問題を覚えていた」ことが大きかったです。
iNARTEの試験は、年度によって出題範囲が多少変わるとはいえ、同じ問題や似た形式が繰り返し出ることがあります。
実際、私が再受験したときは、1回目とほぼ同じ問題が多数出題されていました。
1年のブランクがあっても、「あ、この問題見たことある」という既視感がかなりありました。
その結果、落ち着いて取り組むことができ、無事に合格通知を手にすることができました。
合格通知と結果の受け取り方
試験結果はすぐには分かりません。
数週間ほど経ってから、メールで合格通知が届きます。
合格後に紙の合格証が指定された住所に送られてきます。
勉強法というより「現場経験」がカギ
これはあくまで私の感想ですが、iNARTEの勉強は「座学」というより現場経験そのものが試験対策になります。
たとえば:
- EMC試験で使用する測定器(LISN、アンテナ、シールドルーム)の扱い
- イミュニティ試験の手順や試験設定の根拠
- ノイズ源の特定と対策手順
など、現場で日々やっている内容がそのまま問われるイメージです。
つまり、EMC従事者であれば、普段の仕事がすでに試験勉強になっているとも言えます。
私も「現場で覚えた知識」と「CECA資料」で十分対応できました。
オープンブック試験の落とし穴
オープンブック試験というのは一見楽そうに見えますが、実は一番厄介です。
理由は、調べる時間が膨大になるからです。
もし規格書をそのまま開いて挑むと、「どの章に何が書いてあるか」を把握していないと即アウトです。
そのため、事前に 参照ページに付箋やインデックスを貼っておくこと が非常に重要です。
「IEC 61000-4-3」の放射イミュニティ試験、「CISPR 32」のエミッション測定条件など、よく出る規格は即座に開けるようにしておくと効率的です。
Web試験特有の注意点
オンライン受験で注意すべき点をまとめておきます。
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)が必須
- パソコンとスマホを同時に使用(監視用カメラとして)
- 試験中の会話・外部音声は禁止
- 画面共有やスクリーンショットも当然NG
特にスマホを固定する位置には注意が必要です。
私は100円ショップのスマホスタンドを使って固定しました。
後、途中で通信がうまくいかず画面更新をしないといけない場面もありましたが、
落ち着いて対処すれば不正行為とみなされないので安心して下さい。
後、監視官は外国の方ですが翻訳をしてくれるので
日本語でチャットしたりすれば大丈夫です。逆に英語でチャットをするとそのまま英語で返信されるので
英語が得意じゃないと困ります。(笑)
今後受ける方へのアドバイス
これから受験を検討している方に、私なりのアドバイスをまとめます。
- CECAのiNARTE資料は必読
→ 出題範囲をほぼ網羅しており、実務にも役立つ内容です。 - 現場経験が一番の勉強
→ 問題文の意図を理解するには、試験より実務を知ることが近道です。 - オープンブックでも準備は必要
→ 規格書の目次を理解し、すぐに開けるようにしておく。 - オンライン試験の環境確認は必須
→ カメラ・通信テストを事前にしておくと安心。 - 一度落ちても気にしない
→ 同じ問題が再出題されることもあるため、再挑戦しやすい。
まとめ:失敗も糧になる
1回目の不合格は正直悔しかったですが、今振り返ると受験そのものが貴重な学びでした。
実務と規格のつながりを再確認できたのは大きな収穫です。
iNARTE EMC Engineerは決して簡単ではありませんが、
**「実務経験を持つエンジニアが国際的に通用する証」**として、挑戦する価値は十分あります。
これから受ける方は、ぜひ焦らず、現場とリンクさせながら知識を整理していってください。
そして、私のように一度落ちても諦めず、再挑戦してみてください。
きっと、その努力は必ず報われます。
おわりに
この記事が、これからiNARTEを受けようとしている方の参考になれば嬉しいです。
EMCエンジニアとして、資格という形でスキルを証明できるのは大きな自信になります。
受験を考えている方は、ぜひKECの公式ページで最新の試験日程を確認してみてください。
あなたの合格を心から応援しています。
ここまで読んで頂きありがとうございました!!
良ければ他の資格体験談もどうぞ!!